2021年06月18日
会員のおすすめ本の紹介(182)
2021年6月の例会で会員から寄せられたおすすめ本の紹介をします。

https://www.kadokawa.co.jp/product/322012000497/
『異端の祝祭』(芦花公園/角川ホラー文庫)
何をやっても上手くいかない人生を送ってきた島本笑美。就職活動も失敗続き。その原因は彼女は物心ついた時から生きている人間とそうでない人間の区別がつかず隙があると異形の者たちにまとわりつかれてしまう。そんな彼女だったが何故か大手企業「モリヤ食品」の若き社長・ヤンに気に入られ内定を勝ち取る。その後ヤンから特別な仕事を依頼された笑美だがそこでは「研修」という名の不可思議な事が行われていた。笑美を心配した兄は主に心霊現象を主に請け負う「佐々木事務所」に調査を依頼するが…
「モリヤ食品」で行われる「研修」という名の儀式に身震いする。笑美の調査を依頼された事務所の所長・佐々木るみと助手の青山が真相に迫る度に想像していなかった恐怖を体験する。
民俗学ホラー要素とカルトな現実的ホラー要素が合体されている作品。エンタメ色もありすごく面白かったです。
著者独特の表現は私の好きな部分であり、それが強調された前作『ほねがらみ』も面白く読めましたがミステリー要素のある『異端の祝祭』が個人的には好みです。
民俗学カルトが好きな方には特におすすめできる1冊です。

https://www.kadokawa.co.jp/product/322012000497/
『異端の祝祭』(芦花公園/角川ホラー文庫)
何をやっても上手くいかない人生を送ってきた島本笑美。就職活動も失敗続き。その原因は彼女は物心ついた時から生きている人間とそうでない人間の区別がつかず隙があると異形の者たちにまとわりつかれてしまう。そんな彼女だったが何故か大手企業「モリヤ食品」の若き社長・ヤンに気に入られ内定を勝ち取る。その後ヤンから特別な仕事を依頼された笑美だがそこでは「研修」という名の不可思議な事が行われていた。笑美を心配した兄は主に心霊現象を主に請け負う「佐々木事務所」に調査を依頼するが…
「モリヤ食品」で行われる「研修」という名の儀式に身震いする。笑美の調査を依頼された事務所の所長・佐々木るみと助手の青山が真相に迫る度に想像していなかった恐怖を体験する。
民俗学ホラー要素とカルトな現実的ホラー要素が合体されている作品。エンタメ色もありすごく面白かったです。
著者独特の表現は私の好きな部分であり、それが強調された前作『ほねがらみ』も面白く読めましたがミステリー要素のある『異端の祝祭』が個人的には好みです。
民俗学カルトが好きな方には特におすすめできる1冊です。
2021年06月17日
会員のおすすめ本の紹介(181)
2021年6月の例会で会員から寄せられたおすすめ本の紹介をします。

https://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594087418
『瞳の奥に』(サラ・ピンバラ/扶桑社ミステリー)
ラストの展開が驚きの一言。
国内エンターテインメント作品になじみのある人の方が受け入れやすい衝撃の展開だと思います。

https://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594087418
『瞳の奥に』(サラ・ピンバラ/扶桑社ミステリー)
ラストの展開が驚きの一言。
国内エンターテインメント作品になじみのある人の方が受け入れやすい衝撃の展開だと思います。
2021年06月16日
会員のおすすめ本の紹介(180)
2021年6月の例会で会員から寄せられたおすすめ本の紹介をします。
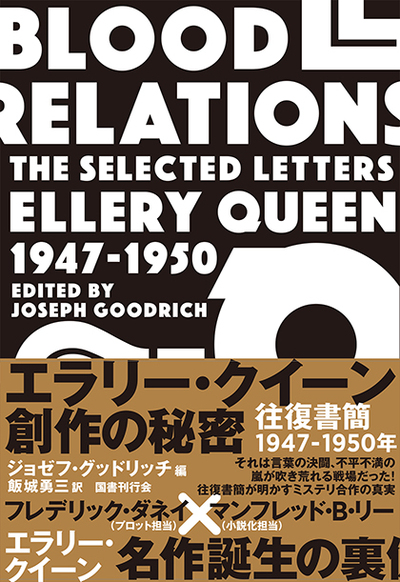
https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336071866/
『エラリー・クイーン 創作の秘密』(ジョゼフ・グッドリッチ編/国書刊行会)
本格ミステリの巨匠エラリー・クイーンがフレデリック・ダネイとマンフレッド・リーという従兄弟の合作ペンネームであったことは良く知られているが、本書はその二人が創作を巡って交わした往復書簡集である。
ミステリ史上に残る名作『十日間の不思議』『九尾の猫』はいかにして生み出されたのか、その舞台裏が赤裸々に明かされる貴重な記録であり、同時にまた大きく異なる才能と個性をもった二人の作家が互いのプライドを賭けてぶつかり合う、壮絶なドラマでもある。
クイーンのファンはもちろんのこと、全てのミステリ好きに読んでもらいたい1冊である。
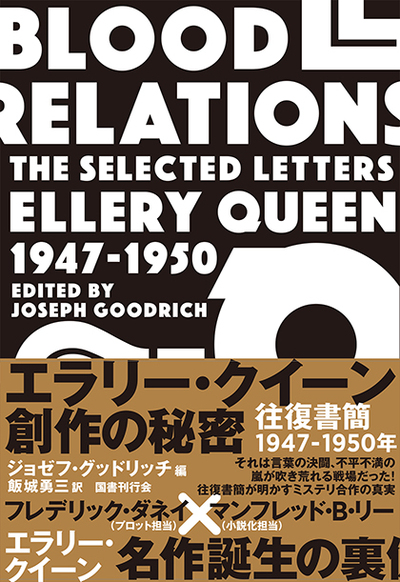
https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336071866/
『エラリー・クイーン 創作の秘密』(ジョゼフ・グッドリッチ編/国書刊行会)
本格ミステリの巨匠エラリー・クイーンがフレデリック・ダネイとマンフレッド・リーという従兄弟の合作ペンネームであったことは良く知られているが、本書はその二人が創作を巡って交わした往復書簡集である。
ミステリ史上に残る名作『十日間の不思議』『九尾の猫』はいかにして生み出されたのか、その舞台裏が赤裸々に明かされる貴重な記録であり、同時にまた大きく異なる才能と個性をもった二人の作家が互いのプライドを賭けてぶつかり合う、壮絶なドラマでもある。
クイーンのファンはもちろんのこと、全てのミステリ好きに読んでもらいたい1冊である。
2021年06月15日
会員のおすすめ本の紹介(179)
2021年6月の例会で会員から寄せられたおすすめ本の紹介をします。

https://www.futami.co.jp/book/index.php?isbn=9784576210667
『風は山から吹いている』 (額賀澪/二見書房)
悲哀の魅力――というといろいろ日本語的に語弊もあるのだが、とにかくこの作品の素晴らしさを誰かと分かち合えればと思う。
大学生・筑波岳が登山中に受けた携帯電話――それは高校時代クライミングで世話になったコーチ、ひどい言葉を投げつけて距離を置いた彼からの突然の電話だった。
その後、そのコーチの死を知る。しかも電話は滑落した時間帯だった。
――彼の死は自殺なのか、事故なのか。
すべてが暴かれる宝剣岳の美しさ。哀しみや苦悩を積み上げてなお、この清々しさを出せる筆力はさすがの一言だ。
穂高の謎、岳の謎、謙介の想い
そして読者にはもういちど冒頭に戻ってもらいたい。
いくつもの想いの重なりが、あの日の帽子の陰影を濃くしていることに気づくだろう。
※※※
ここからは個人的な回想を交えた蛇足である。
本書ではアスリート引退後のセカンドキャリアにも言及している。
胸を打たれたのは、私もかつて選手だったからだ。
中二の時に、4年続けた器械体操から新体操へと転向した。新体操が面白くて仕方のなかった時期で、当然進学も体操で有名な私学を希望した。私の中ではその一択しかなかった。
高校進学に際して両親に頭を下げた。その時に問われたのが人生設計のビジョンだった。
「体操で進学した後のことを考えているのか。お前はどういう人生設計を描いている?」
回答次第では公立への受験となる。この高校に行く目的の明確化。
お金のかかる私立だけに親の問いもシビアだった。
回答をもちろん覚えている。
「高校でタイトルを獲って大学に進み、大学でも競技をしつつ教員免許をとり、体育教師となる。ある程度働いてお金を貯めたら教室を開き、後進の指導に当たる」
なんとご立派な回答だろうか。
しかし大きなタイトルを取れば、それを足掛かりにいろんなチャレンジが出来るようになるだろうと踏んだ。
ちなみに上記回答に即して、現在教室を開いている先輩後輩友人たちは両手では足りない。
そう、ビジョンは完璧だった――はずだった。
まず高校の段階でつまずいた。タイトルを取れるのは団体競技ばかりで個人の成績は振るわない。
それもそのはず、当時ウチの部は団体部門に力を入れていた。またインターハイ個人入賞、ジュニアのアジア選手権入賞、後の五輪日本代表選手など、個人としても有力選手が集まってもいた。
器械体操からの転向組で、ジュニア時のキャリアさえない私など、完全に論外だったのだ。
口幅ったいが、私は突出した柔軟性とアクロバットを最大の武器としていた。が、そこで高得点を得られるルール(当時)ではなかったことも逆風だったのだろう(と思う)
それでも部長をしていたこともあり、当時の団体の成績も良かったことから、体育大学の推薦枠はあった。
実は迷った。ここまでやってきたのだから、という意地も多少あった。
だが自問して苦笑する。自分にキャリアと呼べるものはほとんどない。それに高校生の段階で、既に世界を見つめている周囲の先輩後輩に伍して戦えるのかと。
たいしたキャリアでもない経歴を捨てるのに躊躇はない。
問題は「夢中になった競技」を諦められるか否か、だった。
幼稚園にあがる前から絵本を読んでいた。とにかく本が大好きだった。
深夜に及ぶ練習がつらくても、必ずカバンの中に本はあった。今も姉妹のように親しい友人のひとりは、練習漬けの高校時代に出会っている。これも本が繋いでくれた縁だ。膨大な読書量を誇る彼女は、中学で完成させた小説もどきを読んでくれ、いつか小説家になりたいという夢を最初に後押ししてくれた。
――競技と同じくらい夢中になれるものはまだある。
「教員免許は教員免許でも、体育じゃなくて国語でもいいか」
私の人生の大きな転換期はここだった。
P.114
「あいつはクライミング以外に一生懸命になれるものを、なかなか見つけられなかったんだよ」
P.115
「アスリートのセカンドキャリアは、まず、選手である自分が終わるっていう喪失感を乗り越えるところから始まるんだが(略)…それに時間がかかった……いや、抜け出せていたなったのかもしれん」
引退の理由はさまざまだ。怪我もあろう、結果もあろう、競技自体の選手生命の長短にもかかわるかもしれない。
その後の問題は大きい。
「キャリアを捨てられるか」
「その競技以外に夢中になれるものを見つけることができるか」
過去にいくつものタイトルを獲り、表彰の過去があるならなおさらのこと。
自分が積み上げてきたもをゼロにして違う挑戦が出来るか。
それともそのキャリアを足掛かりに、あくまでもその競技に関わるのか。
セカンドキャリアの問題をしっかりと浮き上がらせているからこそ、この作品は現実味を帯びてなお深みを増す。
彼の死は自殺か、事故か――。
アスリート、かつてのアスリートにはぜひ読んでほしい。種別に関わらず、一緒に登山をしながら己の歩んできた道をなぞっていくような、不思議な感覚を味わえる。
章タイトルの広大さや装丁装画の美しさと、厚みのある作品世界。
今のこのご時世だからこそ、おすすめする一冊だ。

https://www.futami.co.jp/book/index.php?isbn=9784576210667
『風は山から吹いている』 (額賀澪/二見書房)
悲哀の魅力――というといろいろ日本語的に語弊もあるのだが、とにかくこの作品の素晴らしさを誰かと分かち合えればと思う。
大学生・筑波岳が登山中に受けた携帯電話――それは高校時代クライミングで世話になったコーチ、ひどい言葉を投げつけて距離を置いた彼からの突然の電話だった。
その後、そのコーチの死を知る。しかも電話は滑落した時間帯だった。
――彼の死は自殺なのか、事故なのか。
すべてが暴かれる宝剣岳の美しさ。哀しみや苦悩を積み上げてなお、この清々しさを出せる筆力はさすがの一言だ。
穂高の謎、岳の謎、謙介の想い
そして読者にはもういちど冒頭に戻ってもらいたい。
いくつもの想いの重なりが、あの日の帽子の陰影を濃くしていることに気づくだろう。
※※※
ここからは個人的な回想を交えた蛇足である。
本書ではアスリート引退後のセカンドキャリアにも言及している。
胸を打たれたのは、私もかつて選手だったからだ。
中二の時に、4年続けた器械体操から新体操へと転向した。新体操が面白くて仕方のなかった時期で、当然進学も体操で有名な私学を希望した。私の中ではその一択しかなかった。
高校進学に際して両親に頭を下げた。その時に問われたのが人生設計のビジョンだった。
「体操で進学した後のことを考えているのか。お前はどういう人生設計を描いている?」
回答次第では公立への受験となる。この高校に行く目的の明確化。
お金のかかる私立だけに親の問いもシビアだった。
回答をもちろん覚えている。
「高校でタイトルを獲って大学に進み、大学でも競技をしつつ教員免許をとり、体育教師となる。ある程度働いてお金を貯めたら教室を開き、後進の指導に当たる」
なんとご立派な回答だろうか。
しかし大きなタイトルを取れば、それを足掛かりにいろんなチャレンジが出来るようになるだろうと踏んだ。
ちなみに上記回答に即して、現在教室を開いている先輩後輩友人たちは両手では足りない。
そう、ビジョンは完璧だった――はずだった。
まず高校の段階でつまずいた。タイトルを取れるのは団体競技ばかりで個人の成績は振るわない。
それもそのはず、当時ウチの部は団体部門に力を入れていた。またインターハイ個人入賞、ジュニアのアジア選手権入賞、後の五輪日本代表選手など、個人としても有力選手が集まってもいた。
器械体操からの転向組で、ジュニア時のキャリアさえない私など、完全に論外だったのだ。
口幅ったいが、私は突出した柔軟性とアクロバットを最大の武器としていた。が、そこで高得点を得られるルール(当時)ではなかったことも逆風だったのだろう(と思う)
それでも部長をしていたこともあり、当時の団体の成績も良かったことから、体育大学の推薦枠はあった。
実は迷った。ここまでやってきたのだから、という意地も多少あった。
だが自問して苦笑する。自分にキャリアと呼べるものはほとんどない。それに高校生の段階で、既に世界を見つめている周囲の先輩後輩に伍して戦えるのかと。
たいしたキャリアでもない経歴を捨てるのに躊躇はない。
問題は「夢中になった競技」を諦められるか否か、だった。
幼稚園にあがる前から絵本を読んでいた。とにかく本が大好きだった。
深夜に及ぶ練習がつらくても、必ずカバンの中に本はあった。今も姉妹のように親しい友人のひとりは、練習漬けの高校時代に出会っている。これも本が繋いでくれた縁だ。膨大な読書量を誇る彼女は、中学で完成させた小説もどきを読んでくれ、いつか小説家になりたいという夢を最初に後押ししてくれた。
――競技と同じくらい夢中になれるものはまだある。
「教員免許は教員免許でも、体育じゃなくて国語でもいいか」
私の人生の大きな転換期はここだった。
P.114
「あいつはクライミング以外に一生懸命になれるものを、なかなか見つけられなかったんだよ」
P.115
「アスリートのセカンドキャリアは、まず、選手である自分が終わるっていう喪失感を乗り越えるところから始まるんだが(略)…それに時間がかかった……いや、抜け出せていたなったのかもしれん」
引退の理由はさまざまだ。怪我もあろう、結果もあろう、競技自体の選手生命の長短にもかかわるかもしれない。
その後の問題は大きい。
「キャリアを捨てられるか」
「その競技以外に夢中になれるものを見つけることができるか」
過去にいくつものタイトルを獲り、表彰の過去があるならなおさらのこと。
自分が積み上げてきたもをゼロにして違う挑戦が出来るか。
それともそのキャリアを足掛かりに、あくまでもその競技に関わるのか。
セカンドキャリアの問題をしっかりと浮き上がらせているからこそ、この作品は現実味を帯びてなお深みを増す。
彼の死は自殺か、事故か――。
アスリート、かつてのアスリートにはぜひ読んでほしい。種別に関わらず、一緒に登山をしながら己の歩んできた道をなぞっていくような、不思議な感覚を味わえる。
章タイトルの広大さや装丁装画の美しさと、厚みのある作品世界。
今のこのご時世だからこそ、おすすめする一冊だ。
2021年06月14日
会員のおすすめ本の紹介(178)
2021年6月の例会で会員から寄せられたおすすめ本の紹介をします。

https://www.futami.co.jp/book/index.php?isbn=9784576210650
『幻視者の曇り空』 (織守きょうや/二見書房)
ミステリなのでネタバレを避けてなんとか感想を書ければと思う次第ではありますが、これがいつも難しい。
出来ればお読みになってからをオススメ。
「だまされたよね」と言いあいたい。
久守は幻視者だ。いろいろなものが視える。その彼が、巷を騒がせる連続殺人犯と思しき人間をみつける。もちろん幻視だ。
さて犯人は解っている。問題はどうやって警察を動かすか。
証拠を見つけるために、彼に近づく。
だが彼はとても感じがよく、しかも才能だってある。こんな友人がいる毎日は楽しいはずなのに、彼は殺人者なのだ。
――その笑顔は本物なのか、それとも本当の顔は別にあるのか。
そのかかわりの中で、もしかしたら止められるかもしれないという期待も抱く。
久守の行動は読者の予想と希望だ。いくつかの予想と、その反転。こうなるだろうなと仮定するものが、裏切られていく。一緒になって絶望し、また期待する。心地よく裏切られる。その繰り返しが楽しい。
ミステリの面白さを違った角度から見せてくれる作品である。
幻視者の幻視に嘘はない。それを上手く利用してミステリに仕立てる手わざと、結末の心地よい騙され方に、誰かとネタバレのうえで語りたくなる一冊だ。
装丁装画のインパクトも含め!
ちなみにこれを読んでカレーを、それもとても美味しいごはんで食べたいと思ったのは、私だけではないと信じたい。

https://www.futami.co.jp/book/index.php?isbn=9784576210650
『幻視者の曇り空』 (織守きょうや/二見書房)
ミステリなのでネタバレを避けてなんとか感想を書ければと思う次第ではありますが、これがいつも難しい。
出来ればお読みになってからをオススメ。
「だまされたよね」と言いあいたい。
久守は幻視者だ。いろいろなものが視える。その彼が、巷を騒がせる連続殺人犯と思しき人間をみつける。もちろん幻視だ。
さて犯人は解っている。問題はどうやって警察を動かすか。
証拠を見つけるために、彼に近づく。
だが彼はとても感じがよく、しかも才能だってある。こんな友人がいる毎日は楽しいはずなのに、彼は殺人者なのだ。
――その笑顔は本物なのか、それとも本当の顔は別にあるのか。
そのかかわりの中で、もしかしたら止められるかもしれないという期待も抱く。
久守の行動は読者の予想と希望だ。いくつかの予想と、その反転。こうなるだろうなと仮定するものが、裏切られていく。一緒になって絶望し、また期待する。心地よく裏切られる。その繰り返しが楽しい。
ミステリの面白さを違った角度から見せてくれる作品である。
幻視者の幻視に嘘はない。それを上手く利用してミステリに仕立てる手わざと、結末の心地よい騙され方に、誰かとネタバレのうえで語りたくなる一冊だ。
装丁装画のインパクトも含め!
ちなみにこれを読んでカレーを、それもとても美味しいごはんで食べたいと思ったのは、私だけではないと信じたい。
2021年06月13日
会誌『雨中の伽』創刊号を発行しました
佐賀ミステリファンクラブの会誌『雨中の伽(うちゅうのとぎ)』創刊号を発行しました。

・サイズ:A5
・ページ数:236p
●価格
1冊当たり1,200円(税、送料込み)
●販売サイト
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B38CX6R7
【目次】
ページ番号、表題、著者
006 巻頭言 諸岡秀孝
008 ミステリいろは集 竹本健治
020 東京からはるばる参加するのはなぜ?ワクワク佐賀ミス体験記1 如月春日
026 ジョン・ディスクン・カーを読んだ少女 月乃みと
038 私のトラウマ映画 小副川千鶴
042 ~ミステリテーマのボードゲーム4選~ 岩本直也
053 第3回ミステリー作家トークショー&サイン会in 佐賀市 田辺イチロウ
064 チェスター・ハイムズ覚え書き 松岡元樹
074 『神遊び』と『奇譚蒐集録~弔い少女の鎮魂歌~』における相似的関係についての考察 宮田義弘
081 鬼の攪乱 貫く捜査 薗田竜之介
105 オカメハチモク 清水朔
111 本日の献立 宮田義弘
116 SF的小(笑)ート『人類存続判定委員会』 有無同
137 ZOOM殺人事件 瑠璃野律也
230 佐賀ミステリファンクラブ活動記録

・サイズ:A5
・ページ数:236p
●価格
1冊当たり1,200円(税、送料込み)
●販売サイト
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B38CX6R7
【目次】
ページ番号、表題、著者
006 巻頭言 諸岡秀孝
008 ミステリいろは集 竹本健治
020 東京からはるばる参加するのはなぜ?ワクワク佐賀ミス体験記1 如月春日
026 ジョン・ディスクン・カーを読んだ少女 月乃みと
038 私のトラウマ映画 小副川千鶴
042 ~ミステリテーマのボードゲーム4選~ 岩本直也
053 第3回ミステリー作家トークショー&サイン会in 佐賀市 田辺イチロウ
064 チェスター・ハイムズ覚え書き 松岡元樹
074 『神遊び』と『奇譚蒐集録~弔い少女の鎮魂歌~』における相似的関係についての考察 宮田義弘
081 鬼の攪乱 貫く捜査 薗田竜之介
105 オカメハチモク 清水朔
111 本日の献立 宮田義弘
116 SF的小(笑)ート『人類存続判定委員会』 有無同
137 ZOOM殺人事件 瑠璃野律也
230 佐賀ミステリファンクラブ活動記録
2021年06月13日
2021年6月の例会を開催しました
佐賀ミステリファンクラブ2021年6月の例会を開催しました。
今月の例会もオンラインで実施しました。
18名の会員の参加と1名の見学がありました。
〇日時:6月13日(日)13時15分~17時分
〇課題本:『第八の探偵』(アレックス・パヴェージ)
〇内容:
①おすすめ本の紹介
②課題図書の感想
③課題図書についてのフリートーク等
読書会では、
・章が短くて読みやすい
・ミステリの裏側を書いた作品
・作中作の中で様々なチャレンジをしている、ここまでのバラエティを出したのは面白い
・まだこんな仕掛けができるとは驚いた
・作中作がふわふわしていて、ギクシャクしているのも作者の狙いか
・贅沢な作りをしていて、コスパが良い
・どんでん返しの連続にいい意味で眩暈がした
・違う視点で再読すべき作品、作者の意図が見えるかもしれない
・現時点では今年のベスト
・クセモノミステリ
・最後の情景は心に残る
・もう少しミステリ内の定義をはっきりしてほしいと感じた
・伏線をもっと貼ってほしい、フェアでないと感じた
・この作品は「本格ミステリ」なのかという疑問が残る
・「本格ミステリ」に慣れていない人が楽しめるのかという疑問が出た
・現代のイギリスで「日本の新本格的」な作品が出てきているのは面白いが、日本の方がより丁寧に作品を作っている
・この題材で日本の作者であれば別の着地点に落ち着いたと思った
・イギリスらしい作品を書いてほしいと感じた
・日本のミステリが進んでいると感じられた
・目次が無い、原書も目次が無いのか気になる
・ある部分の意図を作者に聞いてみたい
・「色」にもっとこだわりを持ってほしい
・中途半端に感じる部分もあった
などの意見が出ました。
その他、日本のミステリのガラパゴス化、日本のミステリ読者のレベルの高さ、作品中の名前の表記、ルビの話にも話が及びました。
本を多人数で多角的に読むことで、様々な意見が出て、読書会の醍醐味を味わいました。
今月の例会もオンラインで実施しました。
18名の会員の参加と1名の見学がありました。
〇日時:6月13日(日)13時15分~17時分
〇課題本:『第八の探偵』(アレックス・パヴェージ)
〇内容:
①おすすめ本の紹介
②課題図書の感想
③課題図書についてのフリートーク等
読書会では、
・章が短くて読みやすい
・ミステリの裏側を書いた作品
・作中作の中で様々なチャレンジをしている、ここまでのバラエティを出したのは面白い
・まだこんな仕掛けができるとは驚いた
・作中作がふわふわしていて、ギクシャクしているのも作者の狙いか
・贅沢な作りをしていて、コスパが良い
・どんでん返しの連続にいい意味で眩暈がした
・違う視点で再読すべき作品、作者の意図が見えるかもしれない
・現時点では今年のベスト
・クセモノミステリ
・最後の情景は心に残る
・もう少しミステリ内の定義をはっきりしてほしいと感じた
・伏線をもっと貼ってほしい、フェアでないと感じた
・この作品は「本格ミステリ」なのかという疑問が残る
・「本格ミステリ」に慣れていない人が楽しめるのかという疑問が出た
・現代のイギリスで「日本の新本格的」な作品が出てきているのは面白いが、日本の方がより丁寧に作品を作っている
・この題材で日本の作者であれば別の着地点に落ち着いたと思った
・イギリスらしい作品を書いてほしいと感じた
・日本のミステリが進んでいると感じられた
・目次が無い、原書も目次が無いのか気になる
・ある部分の意図を作者に聞いてみたい
・「色」にもっとこだわりを持ってほしい
・中途半端に感じる部分もあった
などの意見が出ました。
その他、日本のミステリのガラパゴス化、日本のミステリ読者のレベルの高さ、作品中の名前の表記、ルビの話にも話が及びました。
本を多人数で多角的に読むことで、様々な意見が出て、読書会の醍醐味を味わいました。






